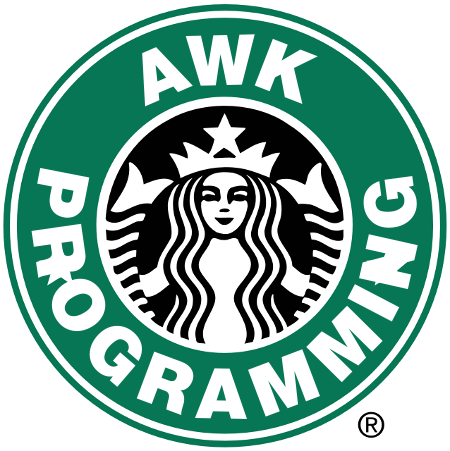 awk
awk Windowsでawkを便利に使う-1
awkを活用するawkをWindowsで使う為の環境づくりを動画でYouTubeにアップロードしました。聞きながら見るという方法が一番無駄がないので音声でナレーションを付ければ良いのですが、マイクの音質が悪いのでコメントを字幕として設定して...
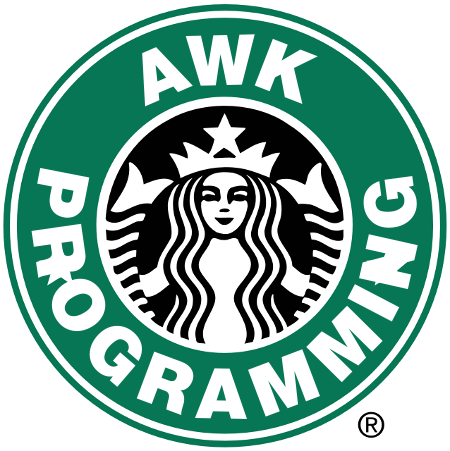 awk
awk 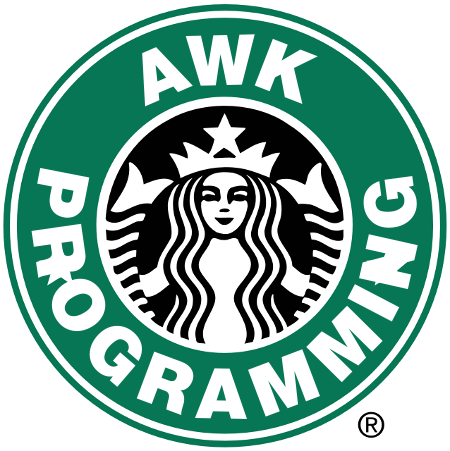 awk
awk 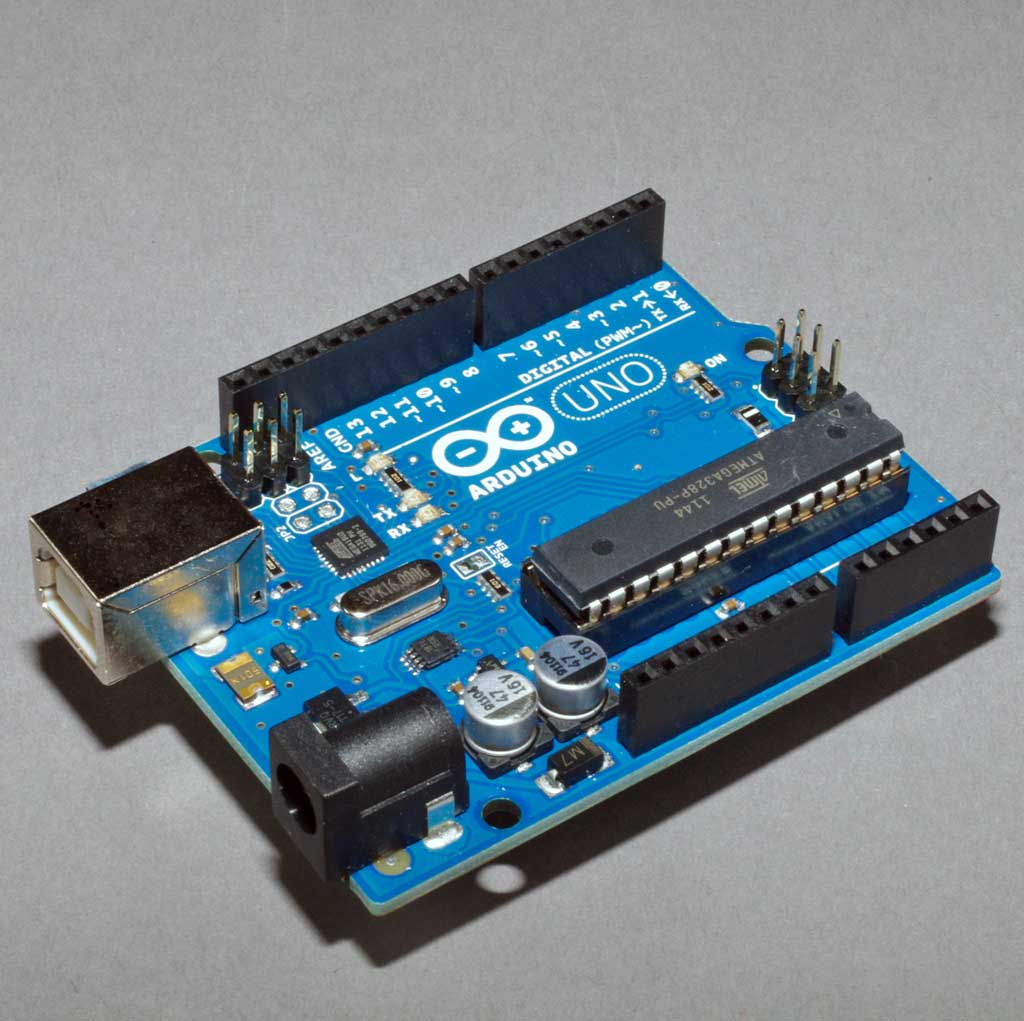 PC・Server
PC・Server 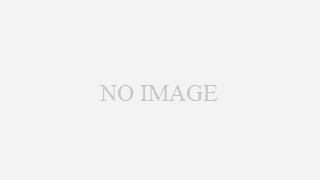 PC・Server
PC・Server