 IT系ニュース
IT系ニュース Becky!とGmail(Google Apps)の組み合わせはイマイチ
Becky!との付き合いは長いのですが、スマートフォンを利用する事もありメーラーは基本的にIMAPで使用することになり、また、仕事用のメールをGoogle Apps(Gmailサーバー)で使っている事もあって、Becky!では非常に不便な思...
 IT系ニュース
IT系ニュース  PC・Server
PC・Server  PC・Server
PC・Server 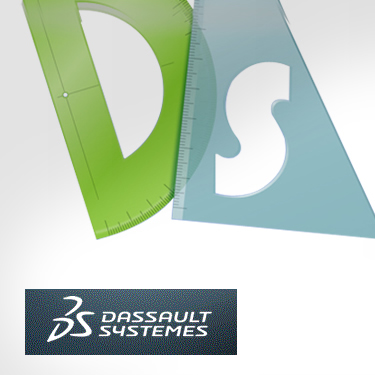 PCツール
PCツール 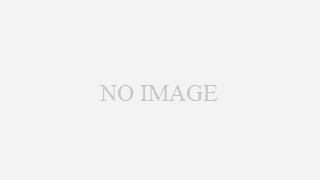 PC・Server
PC・Server