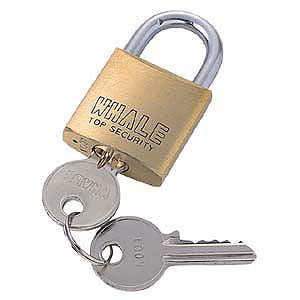 IT系ニュース
IT系ニュース Gmail宛にメールが届かないと困るのでメールサーバーを「SPF」「DKIM」「DMARC」「BIMI」対応させた~さくらのメールボックス
メールサーバーのセキュリティ設定独自ドメインのメールサーバーとして使用している「さくらのメールボックス」さんからメールサーバーセキュリティ(送信側)の強化のお知らせが来たので、調べながら対処することにしました。大した手間はかかりませんでした...
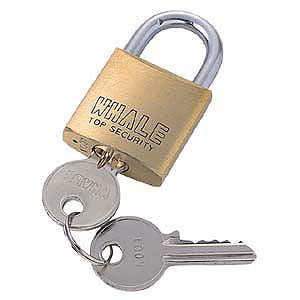 IT系ニュース
IT系ニュース 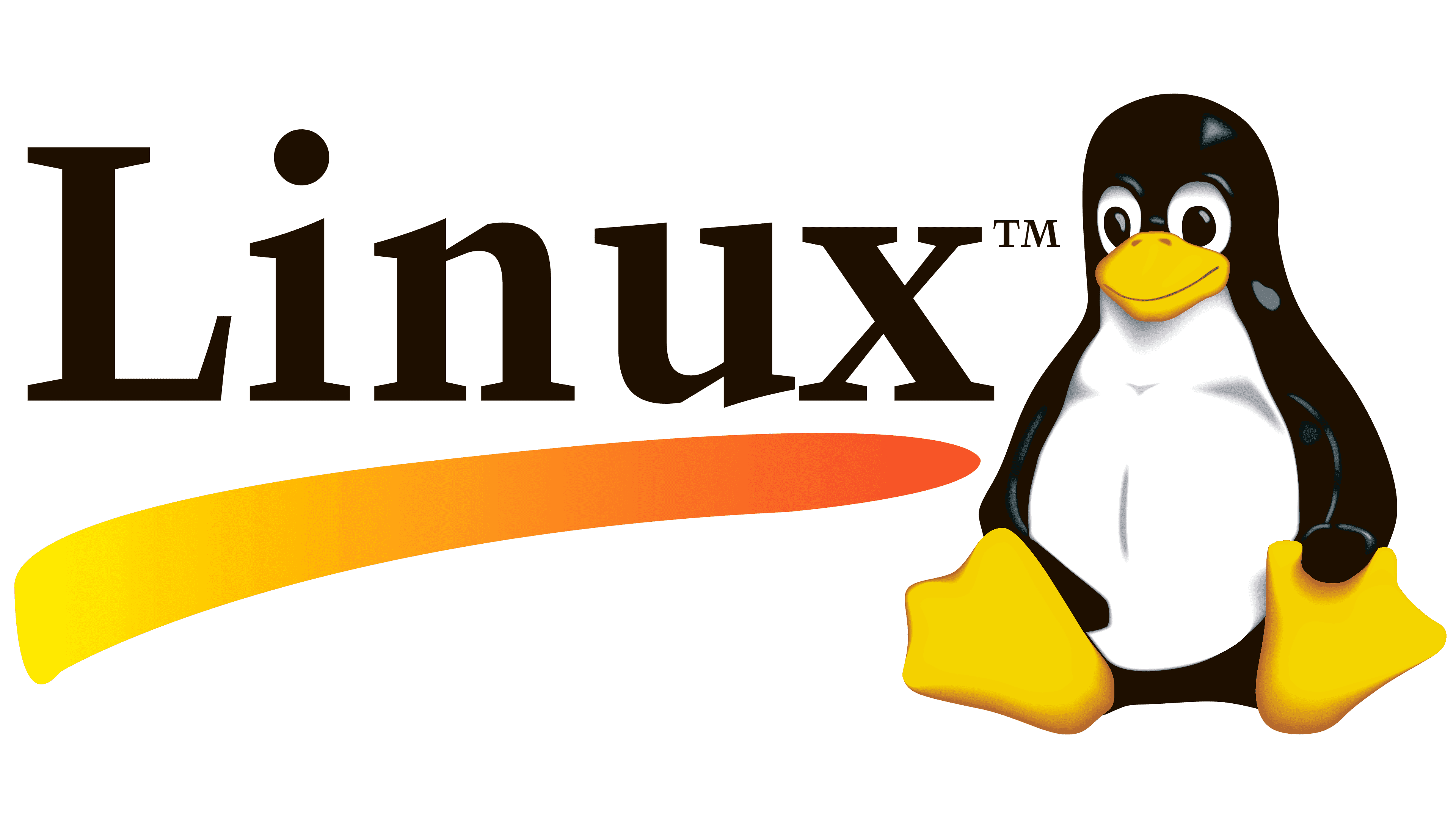 awk
awk  スタッフ日誌
スタッフ日誌 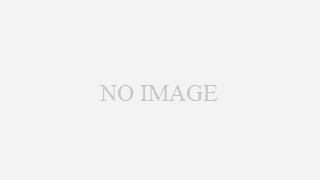 PC・Server
PC・Server