 PC・Server
PC・Server お名前VPS上のWindowsにFilezilla Server
先日から、お名前.comのVPS上にWindowsをインストールして、Windowsアプリによる監視カメラ録画を稼働させっぱなしにしています。カメラ録画はVPSのスペック的にもかなり余裕なのでネットワークカメラの録画用途には最適という感じで...
 PC・Server
PC・Server  PC・Server
PC・Server 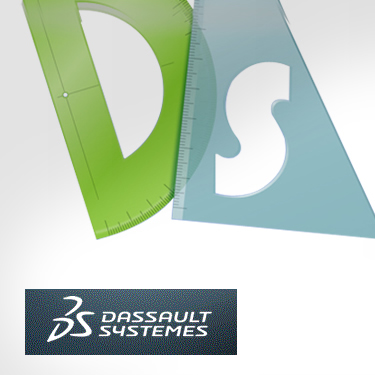 PCツール
PCツール 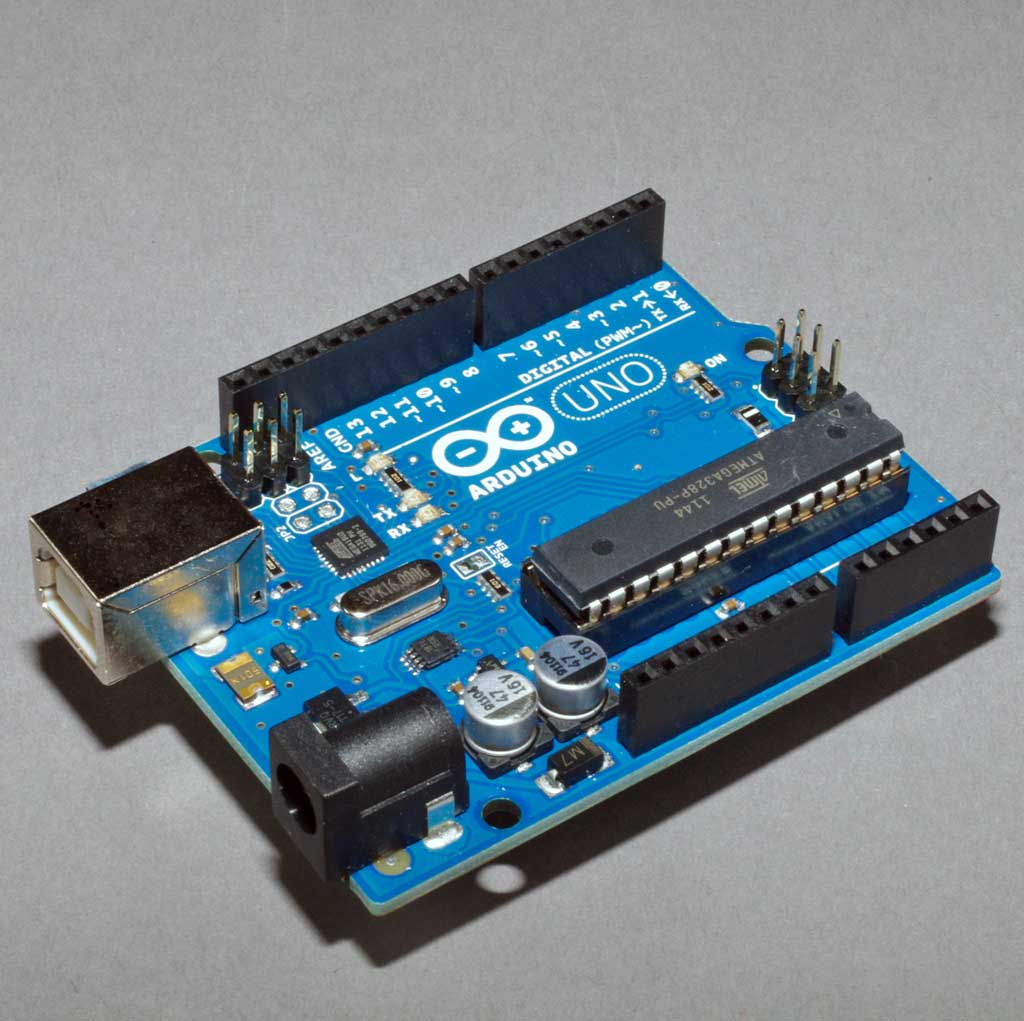 PC・Server
PC・Server  PC・Server
PC・Server